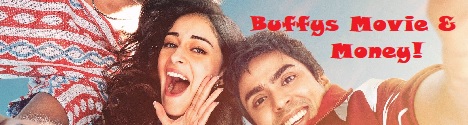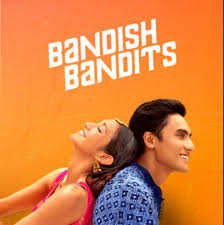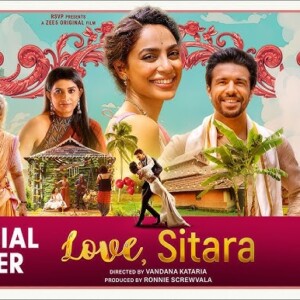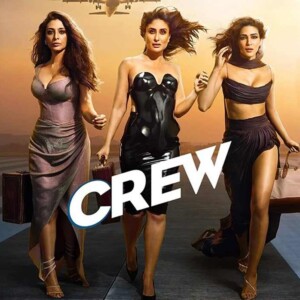映画・ドラマ評:「ジディ・ガールズ ~戦うZ世代女子~」(2025)
「映画秘宝」の連載コラム「映画とカルチャー」を抜粋したものです。
インドでは、年々、Z世代の女性を描いた配信作品が多くなってきている。「女子高生は泣かない」や「ミスマッチな関係!?」もそうだ。その理由は、大衆娯楽の場合、規制されてしまう描写や表現が配信では可能となってくるからだ。だからといって、極端に過激だったり、誇張されたフェミニズムといったものではなく、若い世代からのリアルな主張として描かれている。
ところがそれを良いと思っていない人たちも一定数いて、未だに男性優位主義を掲げ、自己主張をする女性たちに対してフェミナチと言ったりもしているし、一番多いのは、「私はわかっています」と言いながら、女性に古風なものを求める隠れ女性蔑視。これはどこの国も同じに思える。
そもそも女性が声を上げることを”フェミニズム”という特殊なものとして捉えてしまうこと自体が問題であり、ひとりの人間としての主張であること、逆にフェミニズムと表現するべき境界線がどこにあるのかといった、デリケートな部分を描いているのが、Amazonプライムドラマ「ジディ・ガールズ ~戦うZ世代女子~」だ。
さて今作は、自由と個性を重んじる女子学園「マティルダ・ハウス」の生徒たちが、性教育としてポルノ映画を観ていたことがネットで拡散され、それが不適切な行動だと報道されるほどの大問題に発展しまったことから物語が展開される。
その出来事がきっかけとなり、学園の自由が抑制されいってしまうなかで、声を上げることの意味を解いていくのだが、自己主張を壁にして、秩序を無視し、何でもかんでも発言して、それが認められなければ”自由”ではない。という考え方への疑問点も投げかけている。また一方で、自己主張よりも純粋に勉強がしたくて学校に通っているという生徒も一定数いるわけで、そことのバランスをとることも難しい。つまり平等な世界とは何かを、Z世代の様々な視点から描いているのだ。
例えば車椅子のワリカは、父親が有名な活動家であるからこそ、声を挙げることの重要性と同時に、危険性も熟知している。そのことから様々な問題から距離をとってきた。周りが何とか処理してくれるから、それを待っていればいいという考え方だったわけだ。しかし、より身近な問題として直面したとき、女性という以前に、ひとりの人間として声を挙げなければ、国や人々の意識は変わらないといった心情に変化をしていく境界線を上手く落とし込んだキャラクターであった。
そんなワリカを演じたディーヤ・ダミーニは、今作が初めてのドラマ出演となる。ほかのメインキャラクターも、ほとんどが無名。演技が初めてという俳優も少なくないというのに、それを感じさせない見事な演技力という点も大きな見所で、今後、インドエンタメ界を担うであろう逸材が揃っている。
全体的に観ると、描いていることは、どことなくグレタ・ガーウィグの香りがするかもしれない。だからこそ『バービー』(2023年)のように、インドエンタメファンだけではなく、多くの人に幅広い議論を交わしてもらいたい作品なのだ。